この本は2011年11月に出版されたが、それまでに出版された武田の本の中でも、問題点が大きいと考えた。特に、第一章には、「青酸カリより2000倍毒性が高いセシウム」というサブタイトルがあるが、これは以下のような問題がある。ここでは特にこの点について検証してみた。
Cs-137が0.1mgあった場合、その放射能は約320MBqに相当する。福島第一原発事故直後の汚染では、最も高い値で0.31MBq/kg程度の観測があったが[1]、この土壌を集めたとしても、1トン程度の重量が必要になる。計算は成り立っていても、現実的な環境中の濃度を前提にすると、極めて非現実的な想定を置かないと到達しない。またCs-137の放射性物質(非密封線源)を、320MBqを食事や飲料として経口摂取したときの預託実効線量(50年間の積算線量:E(50))は、ICRPの成人の係数 1.3×10-8Sv/Bqを用いると、約4.2Svとなる。ヒトが4Svを瞬時に浴びれば、その50%が60日以内に死に至る(LD50/60という指標で表す)ことが知られているが、内部被曝のときに計算する預託実効線量E(50)は「50年積算」の指標であり、急性被曝の指標であるLD50/60とは異なる量であり、同列に比較することは適切ではない。著者は、青酸カリを一括に摂取したときの50%の致死量が200mgであることと、このE(50)が4Svに達することをもって「青酸カリより2000倍毒性が高いセシウム」と表現したのだと思われるが、比較している量が適切ではなく、前提となる時間スケールや作用機序が異なるため、問題があると言わざるを得ない。さらに、成人の体内ではCs-137の実効半減期は、約110日のため、内部被曝を考えた場合でも、初めの60日に寄与する線量は、1-(1/2)60/110=0.32の計算から、E(50)の約3割に過ぎない。このため、60日間で4Svに至るには、経口摂取する放射能は、さらに3〜4倍が必要になると言える。また、万が一、Cs-137の大量摂取の事故が起きた場合も、プルシアンブルーの早期投与で実効半減期を短縮し線量を大きく低減できるため、被曝致死はゴイアニア被曝事故[2]のような特殊な状況に限られる。
一方で、320MBqのCs-137の密封線源を考えると、1cmの位置では320mSv/hの照射場を作る強い線源であり、この量のCs-137を扱うには、適切な設備を備えた上で、RI法による許可を必要とする。仮に、この密封線源を誤飲したような場合、数日以内に取り出せたとしても局所的に数十Gyの吸収線量が生じ、局所障害によって生命に関わる可能性は高くなる。結局のところ、同じ量であっても、それが一点に集中すれば危険性は高まり、希釈され、少量ずつ摂取されるような状況であれば、影響は相対的に小さくなる。したがって、青酸カリのような化学的な毒物と、環境中の放射性汚染物を、同じミリグラムの物差しで比較することは適切ではなく、前提とする条件(作用するメカニズム、時間スケール、線量指標、致死性の定義)の違いによく注意する必要がある。
[1] T. J. Yasunari, et al., Cesium-137 deposition and contamination of Japanese soils due to the Fukushima nuclear accident, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 108 (49) 19530-19534, (2011), https://doi.org/10.1073/pnas.1112058108.
[2] 原子力百科事典ATOMICA,「ブラジル国ゴイアニア放射線治療研究所からのセシウム137盗難による放射線被ばく事故」, https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-03-02-04.html.
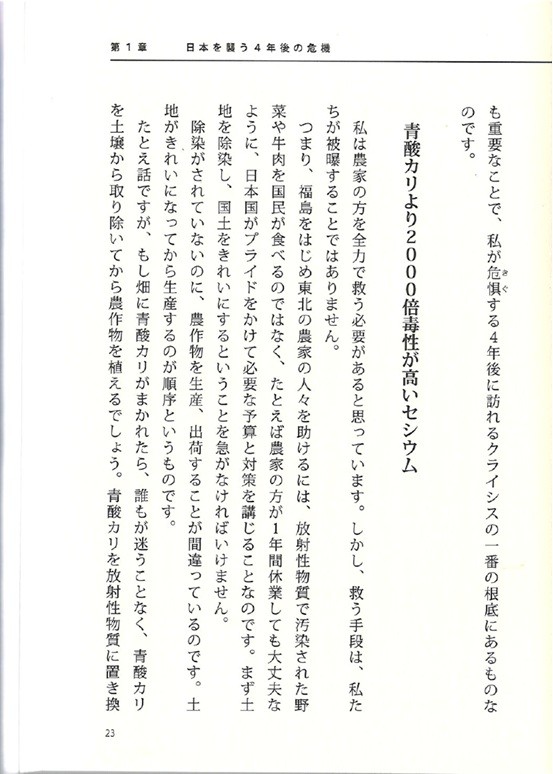
コメント